演題:【いま中小企業に必要なBCPの考え方】
講師:徳島大学環境防災研究センター 湯浅 恭史 先生
日時:令和7年2月18日(火) 16:45~18:00
会場:ザ・グランドパレス 徳島
令和6年11月22日に徳島県で開催された青年部全国大会では「生コンクリート業界として巨大災害を迎え撃つために」をテーマにしたパネルディスカッションで、ファシリテータをお願いした湯浅先生に、BCPの勉強会をして頂きました。
湯浅先生は、事業継続・危機管理を専門分野とし、企業や行政にもご指導されておりますが、今回は生コン業界にも役立つであろう「中小企業のBCPへの取り組み」についてお話し頂きました。
■能登半島地震で起こったこと
・道路の復旧は重要なところから実施されており、過疎地や、迂回路がある道路では修復されていない状態が残っている。
・地面の隆起や亀裂による排水管の被害も甚大であり、断水が長期化する要因となった。
→ライフライン停止の長期化、道路被害によるアクセスの困難さから人口流出が起きている。
→地域内を商圏とするビジネスが多いため、観光産業の停滞、人口流出によって売上が落ちている。
そのような中で、ニーズに合わせた事業継続や、地域外を対象としたビジネスへの転換など、中小企業の取組み例のご紹介がありました。
南海トラフ地震が発生した場合、特に徳島県南部においては、海岸沿いであることや、脆弱な道路網から、能登半島地震と同様の状態に陥る可能性が高く、とても参考になりました。
■BCPが機能した例
事前に離れた地域の同業他社と結んだ協定により事業を続けられた事例、震災マニュアルにより販売が継続できたスーパーマーケットの事例をお聞きして、事前の備えの重要性、ビジネスへの影響を再認識しました。
近隣ではなく商圏の異なる事業者とは協定を結び易く、また震災の影響を同時に受けないため、有効な方策であるとのことでした。
■BCPについて
事業継続計画書を策定しておくことで、初動対応が明確化し、人命と資産を守り、事業を継続しくことができます。
そして、これからの企業は震災に強い企業体質を作り続けられることが大事であり、そのためには、経営環境の変化に対応し続けられる企業文化が必要です。
今後どうしていくべきかを考える際には、フォワードキャスティング(現在の延長線上の方策)ではなく、バックキャスティング(『なりたい姿/あるべき姿』を描いたうえで、そこから逆算して、それを成すために、何をすべきかを段階的に考える)をする必要があります。
また、社会や地域から見た自社の存在意義・役割を明らかにし、地域経済を含めて考えなければならないことを学びました。
■グループワーク
参加者が3グループに分かれて震災への備えを話し合い、以下のまとめを発表して湯浅先生からのコメントを頂きました。
1.生コン工場で、既に、準備していること
・備蓄品(保存食、簡易トイレ)
・避難経路の確認
・製造装置のデータバックアップ
・各社員パソコンの自動クラウドバックアップ
・避難経路スマホアプリの紹介
・災害時に移動できる通行手形
2.生コン工場で、今後、準備すべきと思うこと
・紙の重要書類の電子データ化
・ミキサー車の退避経路
・材料が入手できなくなった場合の、別材料の事前検討
・社員への意識付け
3.生コンクリート工業組合で、準備できることは何か
・各工場の被害状況の収集と、情報共有
・協同組合間の協定、県を超えた協定
・お互いに協力できるような関係づくりをしておく
湯浅先生には、全国大会で専門分野のご講演をしていただくお時間が十分では無かったのですが、今回の勉強会では、能登半島地震で起きている状況や、企業として災害に備えてどのように取り組んでいくべきかの本質的な考えをお聞きすることができて、大変有意義なものになりました。
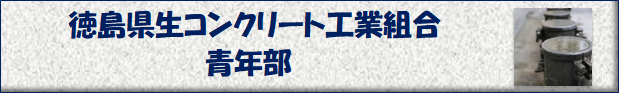






コメントをお書きください